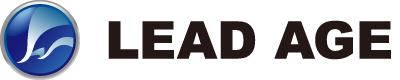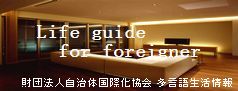ブログ
Blog
2025.07.17
賃貸経営の空室対策で差をつける!管理と設備の見直し術
1. 賃貸経営における空室問題とは?

1.1 空室が続くとどうなる?賃貸経営への影響
賃貸経営において、空室は避けて通れない課題です。
部屋が埋まっていない状態が長引くと、収益が大きく下がり、経営そのものを圧迫してしまいます。
空室が1部屋発生するだけでも、年間で数十万円の損失につながることもあります。
空室が続くと起きる影響を整理すると、次のようなものがあります。
空室が与える主な経営ダメージ
家賃収入が途絶える
収入の柱である家賃が入らなくなるため、毎月の収支が一気に赤字になります。ローン返済や固定資産税などの支払いに支障が出るケースも。
原状回復費用などのコスト増加
退去後のリフォームや清掃など、次の入居者を迎える準備に費用がかかります。空室期間が長くなると、劣化や汚れが進み、追加の修繕が必要になることも。
建物や設備の劣化が進む
人が住まない状態が続くと、風通しや水道の使用が止まり、カビや臭い、虫害などが発生しやすくなります。
こんな状況になっていませんか?
「2ヶ月以上空室のまま、見学も入らない」
「家賃を下げているのに反応が薄い」
「ローン返済額が家賃収入を上回ってきた」
このような状態が続けば、賃貸経営そのものが持続できないリスクも出てきます。
空室の影響を最小限に抑えるには?
空室は完全に避けることはできなくても、長引かせないための仕組みや行動は取れます。
たとえば、
管理会社と連携してこまめな募集活動を行う
募集条件の見直しを定期的に行う
長期入居につながるサポート体制を整える
こういった工夫をすることで、空室リスクをコントロールしながら安定した収益を維持することが可能です。
1.2 空室率の全国傾向とエリア別リスク
空室リスクを正しく把握するには、まず地域ごとの空室率の傾向を知ることが大切です。
日本全国の空室率には大きな地域差があり、賃貸経営の方針にも大きく影響します。
全国平均と都市部の空室傾向
全国の住宅総数に対する空室率(総務省の住宅・土地統計調査によると)は、約13〜14%程度で推移しています。
これは、10戸に1戸以上が空室という計算です。
ただしこの数字は全国平均であり、エリアによって事情は大きく異なります。
都市部(東京・大阪・名古屋など):空室率は比較的低く、10%以下に抑えられている傾向
地方都市・郊外:高齢化や人口減少の影響で、20%以上のエリアも珍しくありません
同じ都道府県でも、駅近か郊外かで空室率は大きく変わります。
地域別に見る空室リスクの特徴
以下のような点に注意すると、エリアごとの空室リスクがより明確に見えてきます。
都心の単身者向け物件:入れ替わりが激しく、定期的なリフォームや設備更新が求められる
郊外のファミリータイプ:長期入居が期待できる一方で、空室になると次が決まりづらい
学生エリア:入学シーズンに集中するため、時期を逃すと1年空室が続くことも
空室率が高い=経営不向きではない
空室率が高い地域だからといって、必ずしも賃貸経営に向いていないとは限りません。
重要なのは、「そのエリアに合った空室対策を打てているかどうか」です。
たとえば、
学生が多い地域なら、家具付きやWi-Fi完備の対応
高齢者が多い地域なら、バリアフリーや見守りサービス
こうした対策を講じることで、空室リスクを大きく下げることができます。
1.3 空室が発生する主な原因とは?
賃貸経営で空室が発生する理由はさまざまですが、原因を正しく理解しておかないと、的外れな対策になってしまいます。
ここでは、よくある空室の原因を整理してみましょう。
空室の原因としてよくあるのは、次の5つです。
1. 家賃設定が周辺相場と合っていない
周辺物件より明らかに高い家賃は敬遠されやすくなります。逆に相場より安すぎる場合も、「何か問題があるのでは?」と不安を与えてしまいます。
2. 室内や設備が古く、魅力がない
築年数の古さよりも、内装や設備の手入れがされていないことが問題です。古くても清潔感があり、使いやすい間取りであれば入居は決まりやすくなります。
3. 写真や募集内容が見劣りする
ネット掲載での第一印象はとても大切です。写真が暗い、間取り図が見にくい、説明文が簡素…こういった要素だけでも選ばれづらくなります。
4. 対応が遅い・悪い管理体制
問い合わせへの対応が遅かったり、内見時の対応が雑だったりすると、入居希望者の気持ちは一気に離れてしまいます。
5. 立地条件が不利で工夫が足りない
駅から遠い、商業施設が少ないなど立地の弱点がある物件は、強みをアピールする工夫が必要です。たとえば「駐車場無料」「静かな住環境」などをしっかり伝えることで、印象を変えることができます。
空室が出る原因は1つではなく、いくつかの要素が重なって発生しているケースがほとんどです。
家賃だけを見直しても効果が薄いのはそのためです。
「家賃設定」「設備の更新」「情報の見せ方」「管理の質」など、総合的に見直すことが空室改善の第一歩です。
2. 空室対策の基本と考え方

2.1 「空室=損失」と捉える思考の重要性
賃貸経営において、空室は「一時的な問題」ではありません。
1日空いているだけでも、その分の家賃収入が失われている=損失が発生しているという意識を持つことがとても大事です。
たとえば、月8万円の賃料の物件が1ヶ月空室だった場合、単純計算で8万円の収入が失われたことになります。
これが2ヶ月、3ヶ月と続けば、24万円・32万円といった金額に膨らみ、ローン返済や固定費に響いてきます。
よくある「空室への甘い認識」
こんな考え方をしてしまっていませんか?
「繁忙期になれば決まるだろう」
「家賃を下げたくないから、このまま様子見」
「一時的な空室だから仕方ない」
このような受け身の姿勢でいると、空室期間はどんどん延びていきます。
空室は自然には埋まりません。対策を打たなければ、何も変わらないまま損失だけが続いてしまいます。
「経営者の視点」を持つことが第一歩
賃貸経営は、単なる不動産の保有ではありません。
「入居者を集め、満足度を高め、長く住んでもらう」ための工夫をすることが、事業としての基本です。
経営者として空室をどう捉えるかで、その後の行動も変わってきます。
定期的な家賃の見直し
内装や設備の改善投資
効果的な募集方法の導入
プロ(管理会社)への業務委託や相談
これらを「費用」としてではなく、「投資」として捉えることが空室を減らし、収益を安定させるコツです。
空室対策は“待つ”ものではなく、“動く”ものです。
この意識を持つだけでも、空室を短縮する第一歩になります。
2.2 家賃設定・ターゲット層の見直し
空室対策を進めるうえで、家賃設定とターゲット層の見直しは欠かせない基本ポイントです。
特に、長く同じ家賃で募集し続けている場合は、知らず知らずのうちに「割高な物件」になってしまっている可能性があります。
家賃が相場とズレていると選ばれにくい
周辺の物件より家賃が高い場合、よほどの魅力がない限り選ばれることは難しくなります。
「同じ広さ・築年数・駅距離」の条件で比較されるため、1000円〜3000円の差でも選ばれなくなることがあります。
一方で、安くすればいいというわけでもありません。安すぎる物件は「なにかあるのでは?」という不安を与えてしまうこともあるからです。
よくある失敗例と改善ポイント
こんな状態に心当たりはありませんか?
1. 過去の相場感にこだわっている
昔の相場で8万円だったから、今も同じ家賃で出し続けている。
→改善策:最新のエリア相場をチェックし、3〜6ヶ月ごとに柔軟に見直す
2. 入居者層を広げすぎている
単身者からファミリーまで歓迎、などとアピールして、かえって誰にも響かない
→改善策:ターゲットを1つに絞り、その層に合った内装・設備を打ち出す
3. 周辺競合物件との差別化ができていない
同じような条件の物件と並べられた時、魅力を伝える要素がない
→改善策:「インターネット無料」「宅配ボックス付き」「家具付き」などを導入し、価値を高める
ターゲット層の再設定が効果を生む
エリアや物件の特徴に合わせて、狙うべきターゲットを明確にしましょう。
たとえば:
駅から徒歩10分以上 → 車所有の社会人をターゲットに、駐車場を無料に
オートロック・宅配ボックスあり → 女性の一人暮らし層に特化
大学近辺のワンルーム → 新入生や留学生向けに家具家電付きに
このように、物件ごとに「誰に住んでもらうか」を定めることで、家賃設定にも説得力が生まれます。
空室対策では、ただ家賃を下げるよりも「ターゲットに合った適正価格」を見極めることが大切です。
2.3 募集方法と広告戦略の工夫
空室を埋めるために、どのように情報を発信するかは非常に重要です。
どんなに良い物件でも、見てもらえなければ入居にはつながりません。
今の時代は「ネットで探して選ぶ」が当たり前。募集方法や広告戦略を見直すことで、空室期間を大きく短縮できる可能性があります。
よくある非効率な募集パターン
こんな募集方法に頼っていませんか?
1. 昔ながらの紙チラシ中心
今はスマホやPCで探す人が大半。紙チラシだけでは情報が届きにくくなっています。
2. 管理会社任せで掲載状況をチェックしていない
写真が古かったり、説明文が簡素だったりすると、内見すらされないこともあります。
3. 物件サイトの露出が少ない
SUUMOやホームズなど主要ポータルサイトへの掲載が少ないと、そもそも検索に引っかかりません。
これらはすべて「物件が選ばれる前に埋もれてしまう」原因になります。
募集力を高める工夫
次のようなポイントを意識することで、広告効果はグッと高まります。
写真の質を上げる(明るく、広角で清潔感のあるもの)
物件の特徴をアピールする文言を入れる(例:ネット無料、ペット可、オートロックなど)
360度カメラや動画を活用する(ネット内見にも対応)
検索キーワードに引っかかるようなタイトル・説明を意識する
また、周辺の仲介会社への営業活動も有効です。
近隣の不動産会社に直接訪問し、「この物件をぜひ紹介してほしい」と伝えるだけでも、紹介される確率が上がります。
複数の媒体を使って露出を広げる
不動産ポータルサイト(SUUMO、ホームズなど)
SNS(Instagramでの物件紹介など)
Googleマップ・MEO対策
仲介業者との連携
自社ホームページやLINE公式アカウント活用
今の時代、ひとつの媒体に頼るより「複数の入り口」を持つことで内見数を増やせます。
募集戦略を見直すだけで、反響数が2〜3倍になることも珍しくありません。
3. 賃貸経営における具体的な空室対策

3.1 ターゲットに合わせた間取り・設備改善
空室が続いてしまう大きな理由のひとつが、「入居者ニーズと物件のギャップ」です。
つまり、今のターゲット層に合っていない間取りや設備が、選ばれにくくしている原因になります。
入居者は「今の暮らし方」に合った物件を求めています。
ターゲット別の改善ポイント
間取りや設備を見直すときは、「誰に住んでもらいたいか」を明確にしたうえで改善を進めることが大切です。
たとえば、以下のような工夫が効果的です。
単身者向け
→ 独立洗面台・浴室乾燥機・インターネット無料など、機能性重視の設備が人気
→ 1Kを1Rにして広く見せる工事も効果的
ファミリー向け
→ 対面キッチンや収納スペースの拡充、子育てしやすい間取り(和室→洋室変更など)
→ 玄関やバルコニーの拡張も喜ばれます
高齢者向け
→ 段差の解消、手すりの設置、浴室やトイレのバリアフリー化などの安全性アップ
こうした改善は、すべて「その層の生活にフィットしているか」を基準に考えることが大切です。
よくある失敗と注意点
間取り改善で失敗しやすいポイントもあります。
1. 万人向けの設備にしてしまう
→ 無難すぎて特徴がなくなる
→ 対策:誰に刺さるのかを明確にする
2. コストをかけすぎる
→ 改装費が回収できない可能性
→ 対策:収支シミュレーションを必ず行う
3. 一部だけ更新してチグハグな仕上がりに
→ キッチンは新品でも壁紙が古いまま…など
→ 対策:印象に直結する場所からまとめて刷新
「間取り・設備」は見た目以上に“暮らしやすさ”に影響する要素です。
ターゲットのライフスタイルに合わせて改善することで、空室期間は確実に短縮できます。
3.2 賃料の見直しと条件変更で差別化を図る
空室が続いている場合、賃料や契約条件の見直しも効果的です。
ただし、単純な値下げではなく、条件の調整で入居のハードルを下げる工夫が大切です。
見直すべきポイント:
家賃が周辺相場とズレていないかチェック
敷金・礼金ゼロで初期費用を軽減
フリーレント(1ヶ月無料)で契約促進
更新料や解約違約金の緩和も検討対象に
ペット可・家具家電付きなどで差別化を図る
注意点:
家賃を下げすぎると収益が圧迫される
競合物件との差別化が曖昧だと効果が薄い
入居者目線で「選ばれる条件」を優先する
条件の柔軟な見直しが、空室対策の一歩となります。
3.3 空室対策としてのリフォーム・リノベーションの活用
築年数が経過した物件でも、適切なリフォームやリノベーションを行えば競争力のある物件に生まれ変わります。
特に築20年以上の物件では、現代の入居者ニーズと大きくズレが生じていることが多いため、見直しの効果は絶大です。
空室対策として有効なリフォーム内容
以下のような工事は、空室対策としてよく採用されています。
水回り(キッチン・浴室・洗面台)の更新
見た目の印象が大きく変わり、清潔感を与えるため非常に効果的です。
壁紙・床材の貼り替え
費用を抑えつつ、部屋全体を明るく見せることができます。アクセントクロスも人気です。
間取りの変更
使いづらい和室を洋室に変更したり、1Kを1Rに変更することで、現代の暮らし方にマッチさせられます。
収納の拡張や設備追加(エアコン、照明など)
特に単身者向けや女性向け物件では、収納力のある部屋が好まれます。
これらは、内見時の印象を大きく左右するため、空室期間の短縮に直結します。
よくある失敗例と対策
リフォームには費用がかかるため、戦略的に進めることが重要です。以下のような失敗も多く見られます。
1. コストのかけすぎで収支が合わない
→ 対策:工事前に収支シミュレーションを行い、数年で回収できるかを確認
2. 見た目だけの変更で生活動線に合っていない
→ 対策:ターゲットのライフスタイルを意識して設計
3. 他物件と似たようなデザインにしてしまう
→ 対策:設備に+αの要素を加える(おしゃれな照明・デザインクロスなど)
小規模リフォームでも効果は出る
必ずしもフルリノベーションが必要というわけではありません。
10万円〜30万円程度の軽微な工事でも、空室対策には十分効果があります。
玄関まわりの照明・ドア交換
キッチンの水栓のみ交換
トイレに温水洗浄便座を追加
このような「ちょっとした改善」が、内見時の印象を左右し、早期成約につながります。
リフォームは単なる修繕ではなく、“空室を埋めるための投資”と考えるのがポイントです。
4. 空室対策で重要な賃貸経営の工夫ポイント
4.1 空室を防ぐための入居者ニーズ分析
空室対策では「入居者が本当に求めているもの」を知ることが先決です。
物件の魅力を高めるには、ターゲットに合った設備や条件が不可欠です。
最近の主なニーズ傾向:
インターネット無料は必須化
宅配ボックスやオートロックが人気
独立洗面台・2口コンロなど設備重視傾向
ペット可や家具家電付きへの需要も増加
よくある注意点:
昔の感覚で家賃や条件を設定している
競合物件との差が把握できていない
入居者の声を反映していない
入居者目線での改善が、空室解消のカギです。
4.2 長期入居につなげる管理とサポート体制
空室を防ぐには、入居後の「満足度」を高めて長く住んでもらう仕組みづくりが必要です。
対応の早さやサポートの充実が、退去防止につながります。
長期入居を促す工夫:
24時間対応のトラブル受付窓口
設備トラブルへの迅速な修理対応
入居者向け特典やクーポンの提供
丁寧な清掃や共用部の美観維持
よくある管理の失敗例:
対応が遅く信頼を失う
小さな不満の積み重ねで早期退去
入居者の声を吸い上げていない
管理レベルの高さは、空室対策にも直結します。
4.3 賃貸経営の収益性を高める空室対策の視点
空室を減らすことは、単に入居率を上げるだけでなく、賃貸経営全体の収益性向上にもつながります。
ムダな支出を抑えながら、安定した家賃収入を得ることが重要です。
収益性を高める空室対策:
原状回復費を最小限に抑える仕様選び(耐久性の高い壁紙など)
高付加価値設備で家賃アップ(宅配ボックス、独立洗面台など)
長期入居を促す管理体制で、入退去コストを削減
空室期間を短縮し、年間の収益ロスを回避
見直すべきポイント:
リフォーム費用が家賃に見合っているか
入退去の頻度が高くなっていないか
設備投資が収益に結びついているか
空室対策は、収益最大化のための“攻め”の施策です。
5. 管理会社を活用した空室対策のメリット
5.1 地域密着型管理の強みとは?
空室対策を任せるなら、地域密着型の管理会社が有利です。
地元に根ざした情報と対応力が、空室解消を後押ししてくれます。
地域密着型管理のメリット:
地域の家賃相場・ニーズに精通している
近隣の仲介会社との関係が強く、紹介力が高い
物件周辺での広告活動(ビラ配り、業者訪問など)ができる
トラブル時も現場対応が早い
大手管理会社との違い:
担当者の顔が見える安心感
一件ごとの対応が丁寧で柔軟
物件ごとの特性に合った提案が受けられる
地域を熟知した管理体制が、入居率アップに直結します。
6. まとめ:空室対策で賃貸経営を安定させるために
空室が出たあとに慌てて動くのではなく、事前の準備と継続的な見直しが空室を防ぐ最大のポイントです。
早めに行うべき対策:
退去連絡後すぐに次の募集準備を開始
原状回復・清掃をスピーディーに完了
家賃や条件を即時に見直し反映
継続的に見直すべき項目:
設備や間取りのニーズへの適合性
募集方法や広告内容の更新頻度
管理体制や入居者満足度の評価
空室対策は一度きりではなく、継続が成果を左右します。
空室対策のご相談はリードエイジへ
管理コストを抑えながら、集客力と管理品質を両立。東京・大阪・福岡・沖縄など全国8エリアで実績多数。
まずはお気軽にリードエイジの公式サイトをご確認ください。