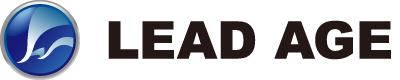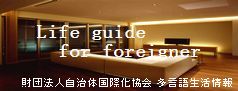ブログ
Blog
2025.07.23
賃貸経営の今後はどうなる?安定収益のための実践戦略
1. 賃貸経営の今とこれから

1.1 現在の賃貸経営の状況とは?
最近、賃貸経営をめぐる環境が大きく変化しています。以前は「建てれば入る」と言われていた時代もありましたが、今は違います。空室率の上昇や入居者ニーズの変化が進み、放置しておくと空室が長期化するリスクが高まっています。
特に地方や郊外では、人口減少や高齢化の影響で入居者の獲得が難しくなっています。一方、都市部では築年数が古い物件が選ばれにくくなり、最新設備の整った物件が好まれる傾向が強まっています。
ここでは、現在の賃貸経営が抱える主な課題と傾向を整理してみましょう。
よくある課題と現状
賃貸オーナーが直面している代表的な課題には、次のようなものがあります。
1. 空室率の増加
入居者の減少や物件の老朽化で、なかなか満室にできないケースが増えています。
2. 家賃の下落圧力
周辺に新築物件が増えると、競争力を失って家賃を下げざるを得ない状況になります。
3. 修繕コストの増加
築年数が進むほど、定期的な修繕やリフォームの費用が重くのしかかってきます。
このような問題を放置すると、収益が年々目減りしていく一方です。特に古い物件を複数所有している場合、維持費だけがかさむ「持ち腐れ状態」になってしまう危険性もあります。
現場でよくあるシーン
たとえば、築30年を超えた2階建てアパートを所有している場合、昔ながらの間取りや和室などが敬遠されることが多くなってきています。加えて、エアコンやWi-Fi環境が整っていないと、内見で即お断りになることもあります。
「家賃を下げる前に、入居者が何を求めているかを知ること」がとても大事です。
賃貸経営の難易度は確実に上がっている
10年前と比べると、収益確保のための努力が格段に必要になっています。ただ、逆に言えば「正しい判断と工夫ができれば、競合と差をつけるチャンスでもある」ということです。
現在のような変化の時代こそ、柔軟な経営視点が求められています。
1.2 賃貸市場に影響する社会的な変化
賃貸経営を取り巻く環境は、社会の動きによって大きく左右されます。近年は、人口動態の変化やライフスタイルの多様化、さらには国の制度改正など、さまざまな要因が絡み合って市場の流れが変わってきています。
とくに注目すべきは、人口減少と高齢化、そして単身世帯の増加です。これらの変化は、今後の賃貸経営に直接影響を与える要素となります。
今後も続く人口減少と高齢化
総務省のデータによると、日本の総人口は2008年をピークに減少傾向にあります。地方を中心に若年層の流出が続き、高齢者の割合がどんどん増えています。
この傾向は、以下のような形で賃貸市場に表れています。
地方では空室率が急増し、物件を維持しても収益につながらないケースが増加
高齢者向け住宅ニーズが高まる一方、バリアフリーなどの改修が必要になる
若者世代の流入がある都市部に人気が集中し、エリア間の競争が激化
高齢の入居者は一度入ると長期入居が期待できる反面、孤独死や緊急対応などへの備えが求められる点にも注意が必要です。
単身世帯の増加がもたらす変化
2020年以降、単身世帯が全体の約40%を超えるまでに増えました。この層の特徴は以下の通りです。
ワンルームや1Kなどのコンパクトな間取りを好む
初期費用を抑えたいニーズが強い
ネット無料・宅配ボックスなど設備の充実を重視する
単身者向けの物件を中心に展開している場合は、こうした細かなニーズを汲み取ることで高い入居率を維持できます。
社会的制度や住宅政策の影響も大きい
たとえば「住宅セーフティネット制度」や「省エネ住宅の推進」といった政策も、今後の賃貸物件に対する評価基準を変えていきます。
省エネ対応(ZEH基準など)の有無で差別化される
国の補助制度を活用してリフォームを進める動きが増加
安心・安全な住宅の提供が求められる傾向が強まる
これからは「どのエリアにあるか」だけでなく、「どんな住まいを提供しているか」も重視されるようになります。
社会の変化を読み解くことが、これからの賃貸経営にとって欠かせない視点です。
2. 今後の賃貸経営に影響を与える主要トレンド

2.1 少子高齢化と単身世帯の増加
今後の賃貸経営を考える上で、「少子高齢化」と「単身世帯の増加」は避けて通れない重要なトレンドです。この2つの社会現象は、入居者層の変化や物件のニーズに直接的な影響を与えており、すでに都市部・地方問わず、大家さんたちの経営方針を大きく変え始めています。
少子化で家族向け物件のニーズが減少
まず、少子化によってファミリー層の賃貸ニーズは徐々に縮小傾向にあります。全国的に見ると、3LDK以上の広い間取りを求める入居希望者は年々減っており、空室が埋まりにくくなっている地域も少なくありません。
その結果、これまで主力だったファミリータイプの物件が競争力を失い、家賃の引き下げや大規模なリノベーションを余儀なくされるケースも増えています。
高齢化で介護対応型物件のニーズが上昇
次に、高齢化の進行により、バリアフリー仕様や緊急通報装置などを備えた「高齢者対応賃貸物件」への需要が高まっています。
高齢入居者に対応するために検討されている主なポイントは以下の通りです。
階段よりエレベーターがある物件を選びたがる
浴室・トイレの段差解消や手すり設置などが求められる
家族が離れて住むケースも多く、緊急通報機能や見守りサービスの有無が判断材料になる
このような対応ができていない物件は、今後敬遠されやすくなる可能性が高いです。
単身世帯の増加で変わる「理想の部屋」
近年は特に都市部を中心に、20代〜40代の単身者が増加しています。この層のニーズは非常に明確で、以下のような傾向が目立ちます。
インターネット無料や宅配ボックスはもはや標準装備
セキュリティ重視(オートロック・防犯カメラ)
生活利便性を重視し、駅近やコンビニ・スーパーへのアクセスが評価される
さらに在宅勤務が一般化したことにより、「ワークスペースが確保できる部屋」という新たな条件も注目されています。1Kやワンルームでも、デスクスペースを確保できる間取りが選ばれる傾向です。
対応しないと埋まらない時代に
昔ながらの感覚で「賃貸物件は家賃を下げれば埋まる」と考えていると、思うように入居者が決まりません。むしろ、ニーズに応じたリフォームやサービス提供ができる物件こそ、安定した経営につながります。
時代の変化に合わせて、入居者像の再定義をすることが安定経営の第一歩です。
2.2 地域格差と空室リスクの広がり
近年の賃貸経営において、「地域による格差」がますます顕著になってきています。
人口の減少や経済の地域集中により、都心と地方、駅近と郊外で入居率に大きな差が生まれているのが現状です。
地域格差が進む背景とは?
全国的に見ると、人口は一極集中の傾向が続いており、特に東京圏・政令指定都市などの都市部には単身世帯や若年層が集まりやすくなっています。一方で、地方都市や郊外エリアでは若者の流出が止まらず、空室が年々増加しています。
その背景には、次のような要因があります。
地方では就業機会が少なく、若者が都市部に移住する
公共交通機関が不便で、生活の利便性が低い
高齢化率が高く、新しい入居希望者が現れにくい
このような地域では、築年数が浅い物件であっても空室リスクが避けられないケースが増えています。
競争力のあるエリアと厳しいエリアの違い
同じ市内でも、駅から徒歩圏の物件と車がないと生活できない場所の物件では、入居希望者の数に2倍以上の差が出ることもあります。
一般的に入居希望者が多いエリアの特徴は以下の通りです。
駅から徒歩10分以内
スーパーや病院、コンビニが近くにある
インターネット環境や宅配ボックスが整備されている
学区や治安の良さに安心感がある
これに対し、厳しいエリアでは「家賃が安くても決まらない」という悩みがつきまといます。
つまり、価格よりも“場所と設備”が選ばれる時代になっているということです。
エリア戦略を間違えると空室リスクが急増
次のような失敗例も少なくありません。
1. 開発計画があると聞いて郊外に建てたが、その後計画が停滞してしまった
2. 築年数が浅いのに、駅から遠くて埋まらない
3. 「周辺も空いているから大丈夫」と放置した結果、家賃を下げても入らない
これらは、需要の読み違いやエリア分析不足によるものです。
エリアごとの人口動態や住宅ニーズを把握することが、安定経営には欠かせません。
とくに今後は、「需要のあるエリアに集中投資する」または「不利なエリアは早期に手放す」といった選択が求められる時代です。
2.3 インフレと金利上昇が与える影響
ここ数年、世界的なインフレの影響を受けて、日本国内でも物価の上昇が続いています。それに加えて、長らく続いた超低金利時代にも変化が見られ、住宅ローン金利や事業用融資の利率がじわじわと上昇傾向にあります。
賃貸経営においては、このインフレと金利上昇の2つが収支に直接影響してくるため、注意が必要です。
インフレの影響:運営コストが上昇
インフレが進行すると、以下のようなコストが上昇します。
建材や設備の価格が上がる(リフォーム費用の増加)
光熱費の負担が増える(共用部電気代など)
清掃・修繕など管理業務の外注費も値上げ傾向
たとえば、トイレの交換費用が2年前より15%上昇していたり、クロス張り替えの単価が1㎡あたり数百円上がっていることも珍しくありません。今までと同じ修繕内容でも、費用が1.2倍〜1.5倍かかるようになってきているのが実態です。
この影響により、従来通りの利回りを確保するのが難しくなってきています。
金利上昇:融資返済の負担が増える
さらに、融資を利用して賃貸物件を所有している場合、金利の変動は収支に直撃します。
特に変動金利で借入をしている場合は、金利が0.5%上がるだけでも年間返済額が数万円〜十数万円単位で増えることがあります。キャッシュフローがギリギリの場合、これが致命的なダメージとなることもあります。
よくある失敗例としては、
1. 購入時に利回りだけを見て借入額を決めた
2. 金利上昇リスクを想定せず、返済計画が甘かった
3. 修繕や空室対応で現金が足りず、追加借入で自転車操業になった
といったパターンが挙げられます。
対策として考えたいポイント
このような環境変化に対して、オーナーが取れる主な対策は次の通りです。
予算の見直しと修繕計画の再検討(必要箇所に集中投資)
金利固定型のローンへの借り換え
設備投資の前に収支シミュレーションをしっかり行う
「今まで通りのやり方」では通用しなくなってきている時代です。
資金繰りにゆとりを持たせることで、突発的な支出にも柔軟に対応できるようになります。
3. 入居者ニーズの変化と設備の最新トレンド

3.1 「選ばれる物件」に共通する設備とは?
今の入居者が物件を選ぶ際、家賃や立地だけでは決まりません。「あるとうれしい」設備の充実度が入居率に大きく関わります。
特に単身者や共働き世帯を中心に、次のような設備が選ばれる条件になっています。
人気の高い設備ランキング(代表例)
インターネット無料(通信費が節約できる)
宅配ボックス(再配達のストレス軽減)
温水洗浄便座(清潔志向のニーズにマッチ)
モニター付きインターホン(防犯意識の高まりに対応)
エアコン・LED照明(初期設備として定着)
こうした設備は初期投資こそ必要ですが、入居期間が長くなる傾向があるため結果的に空室対策になります。
安易に家賃を下げる前に、入居者が「本当に欲しい」と思う機能を整えることが大切です。
3.2 ZEH賃貸やペット共生型の人気上昇
近年、入居者ニーズの多様化により、省エネ性能やペット対応といった付加価値型物件が注目を集めています。家賃が多少高くても「快適で安心できる住まい」を求める傾向が強まっているためです。
人気が高まっている物件タイプ
ZEH賃貸(断熱・省エネ性能が高く、光熱費を削減できる)
ペット共生型住宅(ペット用足洗い場、防音・脱臭設備など完備)
防音強化タイプ(テレワーク普及で需要が拡大)
とくにZEH賃貸は、国の補助金制度を活用しやすく、投資効率の改善にもつながります。
一方、対応が中途半端な場合は「中途半端な高級物件」として敬遠されることもあるため、導入するなら徹底的に設計・設備を揃えることがポイントです。
3.3 よくある設備投資の失敗と対策
設備投資は空室対策に有効ですが、やり方を間違えると「お金だけかかって効果なし」になりがちです。
よくある失敗例とその原因
高額なシステムキッチン導入 → 入居者層と不一致
最新のスマート設備を導入 → 操作が難しく使われない
流行りの設備を複数導入 → 投資額の回収が困難に
こうした失敗を防ぐには、「入居者層に合わせた導入」「費用対効果の事前検証」が必須です。
効果的な対策ポイント
周辺の競合物件を調査し、必要な設備だけを導入する
小規模なリフォーム(照明、クロス、エアコン)でも印象アップが狙える
投資金額と入居率の改善見込みを試算する
無理な設備投資をせず、“必要なものを的確に”整えることが成功のコツです。
4. 今後の賃貸経営を安定させる対策とは
4.1 空室対策として効果的なリフォーム例
古くなった物件でも、的確なリフォームを行えば入居率を改善することができます。
見た目や使い勝手を少し変えるだけで、印象が大きく変わることもあります。
費用対効果の高いリフォーム例
アクセントクロスの導入(部屋の印象がぐっとおしゃれに)
床材の張り替え(フローリング風で清潔感を演出)
水まわりの部分交換(洗面台・トイレの便座など)
注意すべき失敗例
高額な間取り変更で費用倒れ
好みに合わない内装カラーで敬遠される
築古のまま部分的にだけリフォームしてアンバランスに
リフォームは“ターゲット層に刺さること”が最優先です。
内見時に「住んでみたい」と思わせる印象づくりが、空室を埋めるカギになります。
4.2 家賃下落を防ぐ「差別化戦略」
築年数が進むとどうしても家賃の下落が起きやすくなりますが、物件の価値を明確に打ち出すことで“選ばれる理由”を作ることができます。
効果的な差別化の方向性
ペット可物件(希少性が高く、長期入居が期待できる)
女性専用・防犯強化型(特定層の安心感を提供)
家具付き・Wi-Fi付き(初期費用を抑えたい層に人気)
やってはいけない差別化例
一部だけリフォームして他は古いまま
ターゲットが不明確な中途半端なデザイン
家賃だけを下げて訴求力を落とす
差別化のコツは「エリア・ターゲットに合った特化」です。
万人向けではなく、“この人に刺さる”ポイントを明確にすることが重要です。
4.3 IT活用と効率的な物件管理方法
人手不足や遠隔管理の需要が高まる中、ITを活用した賃貸管理の効率化が進んでいます。
時間やコストを削減できるうえ、入居者満足度の向上にもつながります。
導入が進んでいる主なITサービス
スマートロック(内見の無人対応が可能に)
オンライン入居申込・契約(時間の短縮と利便性アップ)
管理アプリやポータルサイト(賃料管理やトラブル対応を一括化)
よくある導入時の注意点
高機能すぎて管理会社が使いこなせない
入居者にとって使いづらいシステムを選んでしまう
複数システムを入れて管理が煩雑に
「使いやすさ」と「費用対効果」を見極めて導入することがポイントです。
無理なく使えるツールから取り入れることで、日々の運営がぐっとラクになります。
5. 長期的視点で考える賃貸経営の将来性
5.1 法人化・相続対策を見据えた経営設計
賃貸経営は長期にわたる事業です。将来の相続や節税を見据えて、法人化や事業承継の準備を早めに考えることが大切です。
法人化による主なメリット
所得分散による節税(家族に給与を支払える)
経費計上の幅が広がる(保険料・車両費なども対象に)
相続税評価の圧縮(不動産保有による節税効果)
よくある失敗例と注意点
節税だけを目的にして法人化し、運営が非効率になる
法人名義で融資が通らず、資金計画が崩れる
相続時に家族が物件をどう扱うか決まっておらずトラブルに
早めの相談と計画的な経営設計がトラブル回避のカギです。
税理士や不動産専門家と連携し、次の世代まで安心して引き継げる体制を整えましょう。
5.2 売却か保有か?今後の判断基準
築年数の経過や収益性の低下により、「この物件は持ち続けるべきか、売却すべきか」という判断に迫られることがあります。
感情ではなく、冷静な数値と将来性をもとに検討することが大切です。
売却を検討すべきタイミング
築25年以上で空室が増えてきた
大規模修繕の費用が収益を圧迫している
利回りが下がり、他の物件への組み替えを検討中
保有継続を選ぶべき場合
エリアの需要が根強く、安定した家賃収入がある
築浅で設備が整っており、入居率も高い
法人経営で長期の資産形成に組み込んでいる
判断の基準は「今後10年間で収支がどうなるか」です。
数値シミュレーションと市場動向をもとに、感情に流されず戦略的に判断しましょう。
5.3 将来を見越した収益プランの立て方
賃貸経営では、「今、利益が出ているから大丈夫」では通用しない時代になっています。将来の空室リスクや修繕費を見越して、継続的に利益が出る仕組みを作ることが重要です。
収益プランを立てる際のポイント
10〜20年単位の長期収支シミュレーションを行う
修繕積立金を年ごとに計画的に確保する
税制改正や金利変動を想定したシナリオを複数用意する
よくある落とし穴
表面利回りだけで投資判断をする
大規模修繕や退去費用を見落として赤字に転落
所得増による課税強化で利益が目減りする
「予測して備える」ことが安定経営の基本です。
専門家のアドバイスを活用しながら、定期的な見直しを取り入れていきましょう。
6. まとめ|今後の賃貸経営で大切な視点
6.1 今日からできる賃貸経営の見直しポイント
変化の激しい今の賃貸市場では、「今すぐできる改善」が将来の安定収益に大きく影響します。まずは現状を把握し、できることから始めましょう。
見直しの第一歩として有効なポイント
空室が続いている物件の競合調査(家賃・設備・立地の比較)
設備の更新優先度チェック(古い順に費用と効果を見積もる)
修繕履歴の確認とスケジューリング(突発対応を減らす)
すぐに実践できる行動例
管理会社との打ち合わせを月1回ペースに変更
募集図面や写真を最新に差し替える
入居者アンケートを取り、満足度や改善点を把握する
小さな見直しの積み重ねが、収益改善につながります。
やみくもに動くのではなく、「今、何が弱点か?」を明確にすることがスタート地点です。
6.2 未来に備えるには「早めの対策」がカギ
賃貸経営は、「困ってから動く」では遅すぎる世界です。空室、修繕、税制、需要の変化など、将来予測に基づいた先手の対策が安定経営の要になります。
今から準備すべき対策の代表例
大規模修繕の10年計画を立てておく
将来の相続や法人化に備えて専門家に相談する
人口動態や再開発など地域の情報を常にチェックする
対策が遅れると起きやすいトラブル
修繕費の積立不足で急な工事費が払えない
空室が増えても対応策がなく赤字に転落
相続時に納税資金や権利分割で揉める
将来の安心は「今日の準備」から生まれます。
変化を恐れず、柔軟かつスピーディに対応できる姿勢が成功のカギです。
資産価値を高める賃貸経営ならリードエイジにお任せください
空室対策や設備投資の見直し、相続対策まで、プロ目線で的確なご提案をいたします。地域特性を活かした実践的なコンサルティングが強みです。
詳しくはリードエイジのホームページをご覧ください。