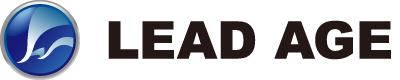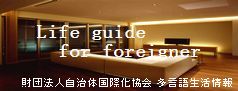ブログ
Blog
2025.07.23
アパート経営の入居率目安とは?95%維持のポイントを解説
1. アパート経営における入居率とは

1.1 入居率とは?基本的な意味と計算方法
アパート経営において「入居率」は、経営状況を左右する大事な指標です。
簡単に言えば、所有している部屋のうち、実際に人が住んでいる割合のことを指します。
まずは基本的な計算式を押さえておきましょう。
入居率(%)= 入居中の部屋数 ÷ 全体の部屋数 × 100
たとえば、10戸のアパートのうち9戸に入居者がいる場合、入居率は90%になります。
9 ÷ 10 × 100 = 90%
このように入居率は一見わかりやすい数値ですが、少し注意が必要です。「高ければ安心」「低ければ失敗」と単純に判断してしまうと、誤解や過剰な対策に繋がることもあります。
こんな失敗が多いです。
1. 計算のタイミングを間違えてしまう
月末時点なのか、年間平均なのかで数値は大きく変わります。
2. 一時的な退去で「低すぎる」と誤認する
繁忙期や転勤シーズンなど、一時的な空室はよくあることです。
3. 全戸リノベ中でも空室扱いにしてしまう
実際には募集していない部屋を「未入居」としてカウントしてしまうケースもあります。
こうした誤解を避けるには、入居率の「意味」と「背景」をセットで理解することが大切です。
入居率という数字は「いつ・どうやって算出されたのか」を見極めることがポイント。
月単位の数値と年単位の平均では印象がまったく違います。
つまり、「95%」という数字ひとつ取っても、その背景を知らずに比較しても意味がありません。
入居率は経営判断の軸になります。正しく把握していないと、必要のないリフォームにお金をかけたり、焦って家賃を下げたりと、判断ミスにつながる可能性もあるので注意が必要です。
1.2 時点入居率と期間入居率の違い
「入居率」と一言でいっても、実は計算方法によって2種類に分けられます。
それが時点入居率と期間入居率です。
この違いを正しく理解しておかないと、データの読み間違いや不要な空室対策に走ってしまう原因になります。
まず、それぞれの意味を見ていきましょう。
時点入居率とは?
ある特定の時点で、どれだけの部屋が埋まっているかを示す数値です。
たとえば「2025年7月1日時点で90%」というように、一日だけの瞬間的な状態を示します。
物件情報サイトや管理会社が提示する入居率は、この「時点入居率」であることが多いです。
期間入居率とは?
1ヶ月・半年・1年など、一定の期間中で部屋がどれだけ埋まっていたかを見る数値です。
たとえば、1年間のうち10部屋のうち延べ9部屋が入居していた場合、「年間入居率は90%」というように算出します。
この2つは似ているようで、意味合いが大きく異なります。
たとえばこんな違いがあります。
空室が1日でもあれば、時点入居率は下がります。
一方で期間入居率は、空室期間が短ければあまり影響を受けません。
こんな場面を想像してください。
退去後すぐに入居が決まるような人気物件の場合、瞬間的には「空室=0人」なので、時点入居率は一時的に大きく下がります。
でも、1年通してみれば「ほとんど空室がなかった」ため、期間入居率は高く保たれていることもあります。
つまり、
「高い時点入居率」=空室が今ほとんどない状態
「高い期間入居率」=長期的に見て安定して埋まっていた状態
このように解釈できます。
入居率を見るときは「時点か期間か?」を必ずチェックするのがポイントです。
特に不動産経営を始めたばかりの方は、「入居率95%」という数値だけを見て安心してしまいがちです。
ですが、何を基準に計算されているのかを確認しないと、誤った経営判断に繋がってしまうこともあります。
1.3 空室率との関係性と混同しやすいポイント
アパート経営に関する指標の中で、「入居率」とよく混同されがちなのが空室率です。
似たような言葉に見えますが、意味はまったく逆。
この2つを正しく使い分けることは、収益の安定化に直結する大切なポイントです。
まず、両者の定義を簡単に整理しましょう。
入居率(%)= 入居中の部屋数 ÷ 総戸数 × 100
空室率(%)= 空室の部屋数 ÷ 総戸数 × 100
つまり、入居率が90%なら、空室率は10%ということになります。
数字的にはちょうど反対の関係にあるんです。
とはいえ、実際の現場ではこの2つが混ざって使われていることも少なくありません。
特に注意したいのが、管理会社や物件情報サイトが出している数値です。
たとえば「空室率10%を維持しています」と書かれていても、それが時点なのか期間なのかによって意味合いが変わりますし、「空室戸数ベース」なのか「面積ベース」なのかによっても印象が大きく変わります。
こんな間違いがよくあります。
1. 空室率を低く見せるために短期募集の空室を除外して計算
2. リノベーション中の空室を「入居中」として誤解させる表記
3. 空室率と稼働率を混同し、過大評価してしまう
これらは、入居率と空室率の定義を曖昧に理解していることが原因です。
「空室率が低い=すぐに満室になりそう」
「入居率が高い=収益が安定している」
という認識は一見正しそうですが、数字の根拠や計算方法を確認せずに判断するのは危険です。
特に投資用物件を検討しているときは、掲載されているデータの「出典」「集計期間」「対象の部屋」など、細かい条件を確認するようにしましょう。
見せかけの数字に惑わされず、根拠のある入居率・空室率を見極めることが安定経営への第一歩です。
2. 入居率の全国平均と経営における目安

2.1 全国・地域別の平均入居率データ(最新)
アパート経営において、「うちの入居率って高いの?低いの?」と気になる方は多いはずです。
そこで重要になるのが、全国の平均入居率とエリアごとの傾向を知ること。
他と比較することで、自分の物件の状況を客観的に判断しやすくなります。
まず、最新データを見てみましょう。
全国の入居率は以下のような水準です。
地域 平均入居率(2023年度)
全国平均 約95.8%
首都圏 約96.4%
関西圏 約95.0%
地方都市圏 約94.5%
このように、全国的に見れば95%前後がひとつの目安になっています。
特に首都圏や大都市圏では96%を超える物件も多く見られますが、地方にいくほど少し下がる傾向があります。
ここで押さえておきたいのは、数値そのものよりも「どのエリアに位置するか」によって相場が変わるということ。
つまり、「全国平均が95%だから94%は低い」と一概には言えません。
たとえばこんな傾向があります。
駅徒歩10分以内・築浅物件は、97%以上の高入居率も多い
地方で築20年以上のアパートは、90%を下回ることも珍しくない
観光地や大学エリアなどは、季節変動が大きくなる
エリアによっては、95%でも「かなり優秀」とされる場合もあれば、逆に「努力不足」とみなされることもあるんです。
こんな失敗もよくあります。
1. エリアの特性を無視して全国平均と比較する
2. 平均値だけを見て、自分の物件を過小評価してしまう
3. 管理会社の数値と統計データを混同して判断する
数値の出典や前提条件をしっかりチェックすることで、無駄な空室対策や不要なリフォームを防げます。
つまり、入居率を見るときは「全国平均」と「エリアごとの傾向」をセットで捉えることが大事です。
2.2 安定経営とされる入居率の基準とは?
入居率は数字で見える分、目標設定がしやすい指標です。
とはいえ、「何%あれば安定経営と言えるのか?」という問いに対して、明確な基準を知らない方も多いのではないでしょうか。
一般的に、入居率95%以上が「安定経営のひとつの目安」とされています。
理由は単純で、空室が5%以下であれば、月々の家賃収入が大きく落ち込むことはなく、収益の予測が立てやすくなるからです。
たとえば10戸中1戸が空室でも、入居率は90%になります。
一見悪くない数値に見えますが、それが半年以上続けば、年間家賃収入の約10%が失われる計算になります。
仮に家賃が月6万円なら、1戸分で年間72万円の損失です。
入居率と収益性の目安を整理すると、次のようになります。
入居率 経営状態の目安
98〜100% 非常に安定
95〜97% 安定経営ライン
90〜94% 改善が必要な水準
90%未満 経営リスクあり
こうして見ると、「95%以上」というのがなぜ重要視されるかがわかりますよね。
こんな失敗がありがちです。
1. 一時的に満室になっただけで「問題なし」と判断する
2. 長期空室があっても、平均で95%に見えるため放置する
3. 満室を目指しすぎて賃料を下げすぎる
入居率が高い=良い経営、という考え方は間違っていません。
しかし、「どう維持するか」「無理なく改善できるか」をセットで考えることが大事です。
特に築年数が経ってくると、自然と入居率は下がる傾向にあります。
だからこそ、満室にこだわるのではなく、95%以上を安定して維持する運用が「堅実なアパート経営」と言えます。
入居率95%以上をキープできるかどうかが、長期的な収益の安定につながります。
2.3 入居率95%を下回ると起こりやすい問題
入居率が95%を下回ると、アパート経営にはさまざまなリスクが現れてきます。
一見、90%台でも「まだ大丈夫」と思われがちですが、収益性や物件の印象にじわじわと悪影響が出るのがこのラインです。
では、実際にどんな問題が起きやすいのかを見ていきましょう。
1. 収益の大幅な低下
空室が1部屋あるだけでも、年間で数十万円の家賃収入が失われます。
仮に10戸中1戸が半年空室になった場合、年間36万円前後の損失になることも。
このような収益のブレが続くと、ローン返済や修繕積立にも影響が出てきます。
2. 空室が空室を呼ぶ負のスパイラル
空室が続くと、物件の外観や雰囲気に「寂れた印象」が出てしまいます。
内見時に他の空室が目に入ると、「人気がない物件なのかな」と感じられてしまうこともあります。
3. 家賃の値下げ圧力が高まる
空室を埋めようとするあまり、家賃を必要以上に下げてしまうケースが見られます。
一度下げた家賃は簡単には戻せないため、長期的な収益低下につながるリスクがあります。
こうした事態は、決して特別なことではありません。
築年数が10年を超えてくると、自然と入居率が落ち始める傾向があるため、早めの対策が重要です。
特に注意したいのが、「満室じゃない=失敗」と捉えてしまい、焦って不要なリノベーションをしてしまうこと。
高額な費用をかけたのに入居が決まらなければ、さらに経営が苦しくなる…という悪循環に陥る可能性もあります。
入居率が下がり始めたときこそ、冷静な対応が求められます。
入居者のニーズを正しく把握し、広告・管理体制・物件改善など、バランスよく対策を打つことが大切です。
必要以上の値下げや改修に走らず、「収益を守るための動き」を意識しましょう。
3. 入居率に影響する主な要因

3.1 エリアと立地条件が与える影響
入居率を大きく左右するのが「エリア」と「立地条件」です。
物件の魅力が同じでも、場所によって入居希望者の数は大きく変わります。
たとえば、以下のような条件が入居率に影響します。
駅から徒歩10分以内かどうか
周辺にスーパーやコンビニがあるか
学校・病院・公共交通機関の利便性
夜道が明るく、治安が良いかどうか
地方エリアでは、車移動が前提になるため「駐車場の有無」も重要です。
また、同じ市内でも地域ごとに人気の差があるため、「需要がある場所か」をリサーチすることが大切です。
エリア選びは経営の土台。立地の良し悪しが入居率を左右します。
3.2 築年数・設備・間取りの古さの影響
築年数が経つにつれ、物件の魅力は徐々に低下します。
見た目だけでなく、機能面や快適さにも影響するため、入居者の判断材料になりやすいポイントです。
築古物件でよく見られる課題は以下の通りです。
ユニットバスや和室など、時代遅れの間取り
インターホンがモニター無しで防犯面に不安
インターネット環境が未整備
外壁・共用部の老朽化で見た目の印象が悪い
築20年を超えると、「古さ」だけで敬遠されるケースも増えてきます。
対策としては、設備の部分的な更新や、間取りの工夫、見せ方の改善が有効です。
築年数は戻せなくても、「古さの見え方」は工夫で変えられます。
3.3 管理体制やオーナー対応の差が招く空室
物件の魅力があっても、管理がずさんだと入居率は維持できません。
入居者は「住みやすさ」だけでなく、「安心して暮らせるか」も重視しています。
空室を招きやすい管理・対応の例は次の通りです。
共用部分が掃除されておらず、ゴミが散乱
修繕の対応が遅く、トラブルが放置される
入居者トラブルへの対応が不十分
退去後のクリーニングが不徹底で印象が悪い
また、オーナー自身の態度や対応によって口コミが広がり、避けられる物件になることもあります。
安定経営には「物件管理」だけでなく、「入居者対応の質」が問われるのです。
良い管理体制は、それ自体が入居者に選ばれる理由になります。
4. 入居率を維持・向上させる具体的な施策
4.1 募集活動の見直し(広告・仲介連携)
空室が埋まらない原因の多くは、「入居希望者の目に物件が触れていないこと」です。
つまり、広告戦略や仲介業者との連携を見直すだけで、入居率が改善するケースは少なくありません。
見直しポイントは以下のとおりです。
ポータルサイトでの物件写真が暗く魅力が伝わらない
間取り図や設備情報が不十分
仲介業者が優先して紹介する条件に合っていない
管理会社が広告更新を怠っている
特に繁忙期には、情報の「鮮度」や「露出度」が差を生みます。
仲介業者との関係性を強化し、魅力が正しく伝わる広告を整えることが大切です。
物件が選ばれるには、まず「見つけてもらうこと」が第一歩です。
4.2 リノベーションや設備改善の効果
空室が長引く原因のひとつが、設備や内装の「古さ」。
必要に応じたリノベーションや部分的な改善は、入居希望者の印象を大きく変える力があります。
効果が出やすい改善ポイントはこちらです。
独立洗面台や温水洗浄便座の導入
古い壁紙や床材の張り替えで清潔感アップ
キッチンの交換やIH化で利便性向上
ダウンライトやアクセントクロスで現代的な印象に
すべてを新しくする必要はありません。
「見える部分」「使う部分」を重点的に改善することがコスパの高い対策になります。
適切なリノベは、空室対策だけでなく賃料アップにもつながります。
4.3 入居者ニーズに応える工夫とは?
入居率を高めるには、「今どんな物件が求められているか」を知ることがカギです。
ニーズに合っていない部屋は、いくら安くしても選ばれません。
最近の入居者が重視するポイントは以下の通りです。
無料インターネットやWi-Fi対応
宅配ボックスやオートロックなどの安心設備
ペット可やワークスペース付きの間取り
内装のオシャレさ・清潔感・SNS映え
入居希望者の多くは20代〜40代。
時代に合った設備やデザインにアップデートすることが重要です。
「自分が住むならどんな部屋がいいか」を考えると、ニーズが見えてきます。
ニーズに寄り添った物件こそが、選ばれるアパートになります。
5. 入居率改善の成功には専門家のサポートが重要
5.1 独学・自己判断では難しい理由
アパート経営の改善を独学で行おうとする方も多いですが、空室対策や入居率アップには専門的な知識と経験が必要です。
思い込みや自己判断が、逆効果を招くこともあります。
よくある自己判断の落とし穴は次の通りです。
リフォームに費用をかけすぎて利回りが悪化
相場より高い家賃設定で入居が決まらない
広告や募集を自分で行い、集客がうまくいかない
管理会社任せにして改善策を講じられない
実際の現場では、賃貸市場や地域ニーズの「見えない情報」が鍵になります。
経験豊富な専門家と連携することで、適切な判断と費用対効果の高い改善が可能になります。
迷ったらプロに相談。それが空室リスクを防ぐ近道です。
5.2 不動産投資成功のカギはパートナー選びにあり
アパート経営の成果は、どのパートナーと組むかによって大きく変わります。
物件選び、入居率の維持、収益改善すべてにおいて、信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
理想的な不動産パートナーの特徴は次の通りです。
市場やエリアに精通し、正確な相場分析ができる
空室対策や管理改善の具体策を提案できる
オーナー目線で収支計画を立ててくれる
賃貸管理・募集までワンストップで対応できる
LEAD AGEのように、投資+運用+改善を一体で支援してくれる会社は心強い存在です。
手間や不安を減らし、長期的な安定経営につなげてくれます。
信頼できるパートナーとの出会いが、不動産投資の明暗を分けます。
6. まとめ:安定したアパート経営のために
6.1 入居率が経営に与えるインパクト
入居率はアパート経営における「収益の心臓部」です。
たった1部屋の空室が、想像以上に大きな影響を及ぼすこともあります。
入居率が経営に与える主な影響はこちらです。
空室1戸で年間数十万円の家賃収入が減少
利回りの悪化により、資産評価が下がることも
ローン返済や修繕費の支払いに余裕がなくなる
空室の長期化で、物件全体の印象も悪化
特に、複数戸を所有しているオーナーにとっては、1〜2戸の空室でも収支に大きなズレが生じます。
だからこそ、入居率は「見るだけ」ではなく「守る・高める」ことが必要です。
安定した入居率こそが、経営を継続させる最大の土台になります。
6.2 今日からできる改善の第一歩
入居率の改善は、いきなり大規模な工事や高額な投資をしなくても始められます。
まずは「今できること」から見直すことが、空室対策の第一歩です。
すぐに実行できるポイントを整理すると次の通りです。
募集サイトの掲載情報を最新の写真と文章に変更
管理会社に反響状況や案内件数を確認・改善依頼
退去予定を把握し、次の募集時期を逆算して準備
周辺相場をチェックし、家賃や条件を柔軟に見直す
これらは大きな費用をかけずにできる実践的な対策です。
特に広告の改善と管理会社との連携強化は、即効性がある部分でもあります。
小さな見直しが、大きな改善のきっかけになります。
空室対策・入居率アップならリードエイジへ。
築年数や立地に関わらず、入居率を高めるノウハウが豊富。
物件の強みを活かした改善提案で収益最大化を目指せます。
ご興味のある方はリードエイジの公式サイトをご覧ください。