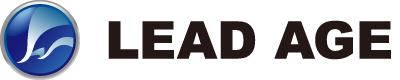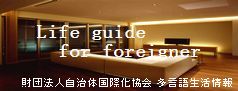ブログ
Blog
2025.08.20
アパート経営で入居率を上げる方法|空室対策と安定経営の実践術
1. アパート経営で入居率を上げる方法と基準値

1.1 入居率の意味と基本の計算方法
アパート経営での「入居率」は、物件の稼働状況を数値で表す大事な指標です。入居率を正しく把握しておくことで、収益性や経営状況の改善ポイントが見えやすくなります。ここでは入居率の意味と計算方法を、具体的に整理します。
まず入居率とは、全体の部屋数のうち、実際に入居している部屋の割合を示します。計算はとてもシンプルで、以下の式を使います。
入居率(%) =(入居中の部屋数 ÷ 全部屋数) × 100
たとえば、20戸のアパートで18戸が入居中なら、入居率は「18÷20=0.9」、つまり90%です。この数字が高いほど、空室が少なく安定した経営ができているといえます。
入居率を確認する際には、次の3つのポイントを意識すると精度が高まります。
計測のタイミングを一定にする(毎月末など)
全部屋数には空室や工事中の部屋も含める
入居中かどうかの基準は賃貸契約の有無で判断する
こんな経験ありませんか?「なんとなく満室に近いだろう」と思っていたら、実際には空室が増えていた…というケースです。数字で管理することで、感覚のズレを防げます。
入居率の正確な把握は、アパート経営の改善に欠かせない第一歩です。数字を明確にすることで、次に打つべき対策が見えてきます。
1.2 全国平均と地域ごとの入居率の違い
入居率を語るときに欠かせないのが、全国平均と地域ごとの差です。基準値を知っておくことで、自分の物件が平均以上なのか、それとも改善が必要なのかがはっきりします。
全国的な賃貸住宅の平均入居率はおおむね95%前後といわれています。ただし、この数値は地域や物件タイプによって差が出ます。
都市部では人口流入が多く、駅近や利便性の高いエリアであれば96〜98%と高水準になることもあります。一方で、郊外や人口減少エリアでは90%前後にとどまるケースもあります。
地域差を理解するためには、次のような視点が役立ちます。
都市部か地方か(人口動態と需要の違い)
物件の築年数や設備レベル
周辺に競合物件が多いかどうか
例えば、駅から徒歩圏内の物件は社会人・学生問わず需要が安定しやすく、入居率も高めになります。逆に、公共交通機関から遠いエリアや築年数が古い物件は、競合との差別化がないと入居率が低下しやすい傾向です。
全国平均や地域特性を知ることは、自分の物件の立ち位置を客観的に把握するための基準になります。ここを押さえておくと、無理な家賃設定や投資判断を避けやすくなります。
1.3 入居率を上げるために知っておくべき基準値
アパート経営で入居率を上げるためには、目指すべき基準値を明確にしておくことが大事です。ゴールがはっきりすれば、そこに向けた施策を無駄なく計画できます。
多くの賃貸経営では入居率95%以上が安定経営の目安とされています。このラインを下回ると、空室による家賃収入の減少が経営を直撃します。特にローン返済や固定費の割合が高い場合、90%を切ると資金繰りに余裕がなくなるケースも珍しくありません。
基準値を設定する際には、次の3つの観点が役立ちます。
損益分岐点の入居率(ローン返済・経費を賄うために必要な水準)
地域の平均入居率(競合との差を把握する)
過去3〜5年の自物件の平均入居率(改善の余地を数値で見る)
例えば、損益分岐点が93%の物件なら、そこを下回らない対策が最優先です。逆に、平均96%の地域で92%にとどまっているなら、競合に劣るポイントを改善する必要があります。
「何%を目指すのか」を決めることは、入居率改善の出発点です。基準値をもとに、効果的な空室対策を選びやすくなります。
2. アパート経営で入居率が下がる原因と改善の方向性

2.1 ターゲット層と物件設備のミスマッチ
アパート経営で入居率が下がる大きな理由のひとつが、ターゲット層と物件設備のズレです。どんなに立地が良くても、入居希望者のニーズに合っていなければ選ばれません。
例えば、社会人単身者向けエリアなのにファミリー向けの広さや間取りになっている場合、需要が少なく空室が長引きます。逆に、学生が多い地域でバス・トイレ別やネット無料がないと、候補から外されやすくなります。
よくあるミスマッチ例は次の3つです。
間取りや広さがターゲット層に合っていない
必要な設備(エアコン、ネット、収納など)が不足
立地に合わない家賃や仕様設定
改善のためには、まず周辺の入居者層をデータや現地調査で把握し、ターゲットに合った仕様に絞ることが重要です。例えば、単身者が多いエリアならコンパクトで使いやすい間取り、家具付きや宅配ボックスの設置が効果的です。
入居者の生活スタイルに寄り添った設備と間取りこそ、入居率を高めるカギです。立地・ニーズ・仕様のバランスを整えることが、空室対策の第一歩になります。
2.2 家賃や初期費用設定が周辺相場と合わない
アパート経営で入居率が伸び悩む理由の一つに、家賃や初期費用が周辺相場と合っていないことがあります。立地や設備に見合わない金額設定は、入居希望者の第一候補から外れてしまう原因です。
例えば、築年数が経っているのに周辺の新築物件と同じ家賃を設定していたり、相場より高い敷金・礼金を要求していたりすると、検索段階で候補から除外されます。最近では「初期費用ゼロ」「フリーレント付き」などの物件も増えており、条件面の柔軟さが集客に直結します。
よくある問題点は次の3つです。
築年数や設備に対して家賃が高すぎる
敷金・礼金が相場より高額
キャンペーンや割引が一切ない
改善するには、まず周辺の賃貸相場を調べ、競合物件との条件差を把握することが大切です。その上で、家賃を下げるのではなく、フリーレント導入や初期費用分割など入居者にとって魅力的な条件を検討しましょう。
金額設定の見直しは、入居率改善に直結する効果的な手段です。条件を柔軟に調整することで、空室期間の短縮が期待できます。
2.3 募集方法や管理体制が不十分
入居率が下がる原因の中でも見落とされがちなのが、募集方法や管理体制の弱さです。立地や家賃が良くても、物件情報が十分に発信されなければ入居希望者の目に留まりません。
例えば、ポータルサイトへの掲載写真が暗く、部屋の魅力が伝わっていなかったり、間取り図がわかりにくいまま放置されていたりすると、内覧希望すら減ってしまいます。また、管理会社との連携が不十分だと、内見対応が遅れたり、募集条件の変更が反映されなかったりと、機会損失につながります。
よくある問題は次の3つです。
物件写真や情報が古いまま更新されていない
募集チャネルが限られていて露出が少ない
内覧対応や問い合わせ対応が遅い
改善策としては、まず最新かつ魅力的な写真や動画を用意し、複数の仲介会社やポータルサイトに掲載することです。さらに、内見希望者がすぐに対応できる体制を管理会社と共有し、情報更新をこまめに行うことが大切です。
募集力の強化と迅速な対応は、入居率向上の即効性が高い対策です。情報の鮮度と対応スピードを意識することで、空室期間を大幅に短縮できます。
3. アパート経営で入居率を上げる具体的な方法

3.1 ターゲット別に必要な設備や間取りを整える
入居率を上げるには、物件のターゲット層に合った設備や間取りを整えることが欠かせません。立地や周辺環境から想定される入居者層を明確にし、その層が求める条件を満たすことで選ばれる物件になります。
例えば、学生が多いエリアでは、Wi-Fi無料や家具・家電付きが喜ばれます。社会人単身者には宅配ボックスや防犯性の高い玄関設備が人気です。ファミリー層なら、収納スペースの充実や子ども部屋の確保が評価されます。
よくある改善ポイントは次の3つです。
ターゲット層のライフスタイルに合わせた設備導入
間取りの使いやすさを重視した改修
利便性や快適性を高める付加価値の提供
設備投資は闇雲に行うのではなく、入居希望者が「ここに住みたい」と思う条件を優先して整えることが重要です。そのためには、周辺の競合物件や入居者アンケートからニーズを把握することが効果的です。
ターゲット層に響く設備や間取りは、広告よりも強力な集客要素になります。住みやすさを第一に考えた改善は、入居率アップにつながります。
3.2 家賃・初期費用の見直しで魅力を高める
入居率を上げるためには、家賃や初期費用を適正化して物件の魅力を高めることが重要です。条件が相場よりも高かったり、初期費用が重く感じられると、検索段階で候補から外れてしまう可能性が高くなります。
例えば、周辺の競合物件より2,000〜3,000円高いだけでも、築年数や設備が同等なら選ばれにくくなります。また、敷金・礼金が高い物件は、初期費用を抑えたい入居者から敬遠されやすい傾向です。
見直しのポイントは次の3つです。
周辺相場を基準に家賃設定を調整する
敷金・礼金を減額またはゼロにする
フリーレントや初期費用分割で負担を軽減する
これらの調整は、必ずしも収益を減らすことにはつながりません。空室期間が短くなれば、長期的には家賃収入が安定し、結果的に収益性が向上します。
条件の柔軟な見直しは、短期間で入居希望者を増やせる効果的な方法です。費用面のハードルを下げることで、より多くの層にアプローチできます。
3.3 外観や共用部の美観維持で第一印象を改善
物件の第一印象は、内覧に訪れた瞬間に決まります。外観や共用部がきれいに整っているだけで、「ここに住みたい」という気持ちが高まり、入居率アップにつながります。
特に多い空室原因のひとつが、外観や共用部の劣化や清掃不足です。エントランスの汚れや郵便受けのチラシ散乱、階段や廊下のくすみなどは、入居希望者にマイナスイメージを与えてしまいます。
美観維持のためのポイントは次の3つです。
定期清掃と点検を徹底する
外壁や共用部の塗装・補修を計画的に行う
照明や植栽で明るく安全な雰囲気を演出する
また、美観維持は入居希望者だけでなく、既存入居者の満足度にも直結します。住み心地の良さは長期入居につながり、結果として空室リスクを下げられます。
外観や共用部の清潔感は、広告よりも早く入居希望者の心をつかむ要素です。第一印象を整えることで、競合物件との差別化が可能になります。
4. アパート経営の入居率アップでよくある失敗と注意点
4.1 設備投資をしすぎて収益を圧迫してしまう
入居率を上げようとするあまり、過剰な設備投資をしてしまうのはよくある失敗です。確かに設備の充実は魅力になりますが、投資額に対して賃料アップや入居率改善の効果が見合わなければ、経営を圧迫する原因になります。
例えば、築20年以上のワンルームに最新型システムキッチンや高級バスルームを導入しても、周辺相場以上の家賃を設定できない場合があります。結果として、費用を回収するのに何年もかかってしまいます。
こうした失敗を防ぐためのポイントは次の3つです。
ターゲット層が本当に求めている設備か見極める
投資額と回収期間を事前に試算する
必要最低限の改善で効果を最大化する
例えば、学生や単身者向け物件なら、キッチンよりもWi-Fi無料化や宅配ボックス設置の方がコストパフォーマンスが高い場合があります。
設備投資は「必要な部分だけに、適切な規模で」が鉄則です。入居者ニーズに直結する改修を選び、収益とのバランスを崩さないようにしましょう。
4.2 家賃を安易に下げてしまい収益性を損なう
空室が続くと、つい家賃を下げて入居者を確保しようと考えてしまいます。しかし、安易な家賃値下げは一時的に入居率を上げても、長期的には収益性を損なうリスクがあります。
例えば、1万円家賃を下げれば年間で12万円の減収です。複数戸で同じ値下げを行えば、その影響はさらに大きくなります。また、一度下げた家賃は元に戻すのが難しく、物件の価値そのものを低く見られる原因にもなります。
この失敗を防ぐための工夫は次の3つです。
フリーレント(家賃無料期間)を活用する
礼金・敷金を下げることで初期費用を軽減する
家具・家電付きやサービス追加で付加価値をつける
家賃額を下げるのではなく、入居者にとって「お得感」を演出することで、競争力を保ちながら空室を埋められます。
家賃は物件のブランド価値を示す重要な要素です。下げる前に、条件や付加価値の調整で勝負できないか検討することが大切です。
4.3 内装や共用部の清掃を後回しにしてしまう
物件の築年数や設備に関係なく、入居希望者の印象を左右する大きな要因が「清潔感」です。特に内装や共用部の清掃が行き届いていないと、「管理が行き届いていない物件」と見なされ、内覧後の成約率が下がります。これは高額なリフォームよりも即効性がある改善ポイントでありながら、意外と後回しにされがちです。
例えば、床にホコリや髪の毛が落ちている、浴室やキッチンに水垢やカビが残っている、廊下や階段にゴミやチラシが散乱している——こうした小さな汚れや乱れが積み重なって、物件全体の印象を大きく損ないます。内覧者はわずか数分で物件を判断するため、この短時間で与える第一印象は非常に重要です。
よくある清掃に関する失敗とその対策は次の通りです。
失敗例1:退去後の清掃が遅れ、募集開始が遅れる
→ 回避策:原状回復と清掃を同時進行し、空室期間を短縮
失敗例2:共用部の清掃頻度が低く、汚れが蓄積
→ 回避策:定期清掃のスケジュールを固定し、写真で清掃状況を記録管理
失敗例3:細部(ドアノブ、照明カバー、巾木など)の汚れを見落とす
→ 回避策:内覧者目線のチェックリストを作成し、細かい箇所まで確認
清掃を強化する際のポイントは以下の通りです。
共用部は毎回の内覧前に簡易清掃を実施
退去から募集開始までの間を極力短縮する
プロのハウスクリーニングを活用し、見えにくい部分も徹底清掃
照明や香りなど視覚・嗅覚にも配慮(暗い印象や生活臭を防ぐ)
清潔感は内覧者に「ここは管理が行き届いている」という安心感を与えます。さらに、既存入居者の満足度向上や長期入居にもつながり、結果として空室リスクを減らします。
清掃は低コストで高い効果を発揮する入居率アップの即効策です。日常的な維持と内覧前のひと手間で、物件の魅力は大きく変わります。
5. アパート経営で日常的にできる入居率向上の工夫
5.1 内覧前に共用部を整える習慣を持つ
入居希望者が物件を訪れる際、最初に目にするのは外観と共用部です。ここで好印象を与えられるかどうかが、その後の内覧の成約率を大きく左右します。きれいに整った共用部は「管理が行き届いている物件」という信頼感を生みます。
例えば、エントランスに落ち葉やゴミがある、郵便受けがチラシであふれている、廊下の照明が切れている――こうした小さなマイナス要素が積み重なると、物件の印象は一気に悪くなります。
内覧前に整えるべきポイントは次の3つです。
エントランス・廊下・階段の清掃と整理整頓
郵便受けや掲示板の不要物撤去
照明・植栽・外観の簡易チェック
この「ひと手間」は費用も時間もほとんどかからず、即効性の高い空室対策になります。内覧の第一印象を上げるだけでなく、既存入居者の満足度維持にもつながります。
第一印象を左右する共用部の整備は、低コストで効果的な入居率アップ方法です。毎回の内覧前に確認する習慣を持つことで、成約率が着実に向上します。
5.2 入居者アンケートで改善点を把握する
入居率を上げるためには、現在住んでいる入居者の声を活用するのが効果的です。実際に暮らしている人の意見は、物件の魅力や改善点を的確に知るための重要な情報源になります。
アンケートで集めた情報をもとに改善を行えば、退去防止と新規入居促進の両方に効果があります。
よくあるアンケート項目は以下の通りです。
住み心地や満足度(騒音、日当たり、間取りなど)
設備やサービスの要望(ネット環境、宅配ボックス、駐輪場など)
共用部や周辺環境の評価(清掃状況、防犯性、利便性など)
活用のポイントは次の3つです。
定期的に実施する(年1回や更新時など)
匿名で回答できる形にする(率直な意見を得やすい)
改善内容を入居者にフィードバックする(信頼感アップ)
入居者の声は改善の最短ルートです。小さな不満を解消するだけでも、入居継続率と紹介による新規入居が増えます。
5.3 季節やイベントに合わせた入居促進策を行う
入居率を上げるには、季節や地域イベントに合わせた募集施策が効果的です。需要のピークや動きやすい時期を狙うことで、短期間での成約率を高められます。
主な施策例は以下の通りです。
引っ越しシーズン(1〜3月):フリーレントや初期費用割引キャンペーンを実施
新生活需要(4月・9月):家具・家電付きプランの提案
地域イベント時:現地内覧会や特典付き見学会を開催
実施のポイントは次の3つです。
時期に合わせたターゲット設定(学生、新社会人、転勤族など)
短期間でインパクトのある特典を用意
告知は複数の媒体で同時に行う(ポータルサイト、SNS、現地広告)
タイミングと施策を組み合わせることで、広告費以上の効果を得られます。計画的なシーズン対策は、空室削減の即効策になります。
6. アパート経営で入居率を上げて安定経営につなげる方法
これまで解説してきた入居率アップの方法を振り返ると、重要なのは「入居者目線」と「計画的な改善」です。設備や条件の見直し、募集方法の工夫、日常の管理体制までバランスよく行うことで安定経営に近づきます。
主なポイントは以下の通りです。
ターゲット層に合った設備・間取りに整える
家賃・初期費用は相場とバランスを取る
共用部・外観の美観維持で第一印象を高める
募集情報の更新と対応スピードを強化する
入居者の声を反映して継続的に改善する
これらを実践する際のポイントは、
数字で現状を把握する(入居率、損益分岐点、空室期間)
短期施策と長期施策を組み合わせる
改善効果を記録して次に活かす
入居率改善は一度で終わる作業ではなく、継続的な管理と工夫が鍵です。日々の取り組みが空室リスクを減らし、安定経営を実現します。
アパート経営で入居率を上げるならリードエイジにお任せください
地域密着の管理力で入居率96%以上を実現し空室を減らします。
賃貸経営の悩みはリードエイジのサポートで解決可能です。